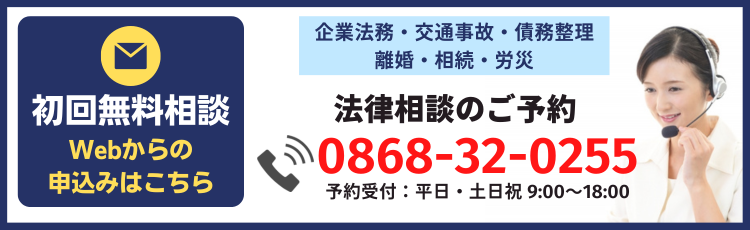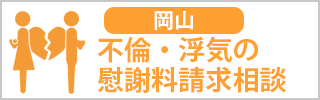これを読めば分かる!離婚を決めたら知っておくべき事とケース別Q&A | 津山・岡山県北の弁護士が徹底解説
「離婚ってしようと思えばすぐに出来るの?」
「離婚時のお金のやり取りや、離婚後の生活が不安だ」
「弁護士は司法書士や行政書士とかと何が違うの?」
「弁護士に相談するメリットがあるの?」
こうお考えの方がほとんどではないでしょうか。こちらのページでは、離婚を検討されている方にとって必要な情報を弁護士の目線で整理いたしましたのでぜひ御覧ください。
目次
離婚の種類
協議離婚
「離婚を考えている」
「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」
「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」
など、夫婦で話し合うものの、お互いの知識が浅い為に難航するケースがよく見受けられます。また離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたく無い」と思われる方が多いのではないでしょうか。
離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。
協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
そして何より、本人同士で話し合う必要が無く弁護士が代理人として進めることが出来ることです。協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。
調停離婚
これは裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
裁判離婚
「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。
法廷で定められている離婚事由
男女の肉体関係伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
裁判離婚の流れ
離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
離婚の理由は様々です。依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも訴状の作成においては弁護士に頼むことをお勧めします。
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。協議や調停よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、費用、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。弁護士の法律の専門家です。納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
離婚とお金の悩み・考えなければいけないこと
離婚で慰謝料が請求できるケースって?
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース:
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース:
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。上記の相場はあくまでも裁判での基準です。また、協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
慰謝料が認められるか認められないか?どれくらい請求できるか?ということについてはケースバイケースです。適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。
財産分与について
・夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい
・離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい
・自分が経営している会社の株だけは取られたくない
・今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。財産分与は、簡単にいうと「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
まず離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。
財産分与の対象となる財産
離婚時の財産分与では、「離婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。
現金、家、自動車、家財道具など全てです。借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。
また下記の2点にも注意が必要です
相手に隠し財産がないか?
場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。当事務所では徹底的に相手の財産については調査して、全ての財産を明らかにすることが可能です。
財産に見落としがないか?
いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。例えば退職金です。退職金も財産分与の対象となります。
次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。
共有財産をどうわけるか
ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。そのため、近年では基本的には5:5でわけることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。ただ5:5というのは裁判になった場合です。
協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由にわけることができます。慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。
当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。
「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもれることになった」
「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」
などの事例も珍しくありません。財産分与でお困りの際は当事務所にご相談下さい。
細かいケース別に見る!離婚後の生活・お金のこと
「離婚後の生活を考えると、子供の養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
養育費に関するご相談も多くよせられます。養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。
【養育費の算定】
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に支払っていくことになります。裁判所が算出表を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づけて算出されることが大半です。
早見表はあくまでも、基準のひとつです。私立学校に通っている場合、入学金が必要な場合など、状況に応じて養育費は変化します。
状況を踏まえ、適正な養育費を受け取るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。
「離婚したら厚生年金ってどうなるの?」
年金の問題は熟年離婚でよく問題とされます。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は厚生年金です。厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるという場合が少なくありません。妻が専業主婦だった場合には、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。
これを年金分割といいます。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。基本的には2分の1で決定することが多いです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、専門の弁護士に相談し、正しく理解することをお勧めします。
「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」
「どのような生活保護制度があるのかわからない」
離婚後の生計をどう立てていくかというのは大きな問題です。特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。このように、離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。
児童1人 月額4万1720円
児童2人 月額4万6720円
児童3人 月額4万9720円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
【母子福祉資金】
現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。
離婚が成立してからが本当のスタートです。当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよくいただきます。
婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
離婚後には様々な手続変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。
日本の医療保険は国民健康保険と健康保険の2つに大別することができ、いずれかの保険に加入しています。保険証は各世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。
ケース①自分自身が会社員または公務員の場合:
基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていると考えられます。その場合は、離婚をした場合であっても特段の手続は必要ありません。
ケース②自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合):
夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出す事で保険料を抑えることができます。なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
ケース③自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合):
自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。
その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をしましょう。
ケース④子供を母親の保険へ移す場合:
子供の保険につきましては、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、子供を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。この場合にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。
「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。
約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。
これを強制執行と呼びます。強制執行で差し押さえられる財産は、
・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金
といったものになります。
強制執行の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門の法律知識や面倒な手続きが必要になります。離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
離婚に関するよくあるご質問
「親権だけはどうしてもとりたい」
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることもできません。
【調停や裁判における親権者を定める基準】
・環境の継続性:
現実に子を養育監護しているものが優先されます。監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。
・監護に向けた状況:
経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。
・子の意思の尊重:
15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。)
・兄弟姉妹関係の尊重:
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。
・親族の協力:
本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られるのであれば、親権が認められることになります
・子供に対する愛情と、養育の意思:
愛情と意思があることは大前提です。親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。
などがあります。
親権問題は状況によって結果が異なります。当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
会うことで子供に悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」
といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
【面会交流の拒否・制限・停止は可能か?】
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、とても重要な問題です。当事者間の感情だけではなく、子供の将来を客観的に考えて決める必要があります。専門の弁護士にご相談ください。
そもそも、離婚交渉について報酬を得る目的で代理業を行うことは、法律上弁護士にしか許されていません。
例えば、協議離婚をご希望の場合でも,完全に相手方と合意できていなければ,直ちに離婚協議書を交わすことはできません。その為、いずれにしても交渉の段階で弁護士の介入が不可欠となります。
離婚調停や離婚訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことも、法律上弁護士にしか許されていません。
離婚協議においては,「もし離婚調停や離婚訴訟に発展すればどうなるのか」という見通しを踏まえて,条件の交渉が行われるため,離婚調停や離婚訴訟に強い弁護士に相談することが重要です。
当事務所は岡山県北地域において,豊富な実績と経験を有しており、皆様の離婚問題を有利に進めさせて頂きます。初回相談料無料ですのでお気軽にお電話ください。
離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から弁護士に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
離婚問題においては,養育費や財産分与等、専門知識が必要な高度な法律問題を含んでいます。仮に、離婚の諸条件に合意してしまった場合、後からこれを争うのは非常に難しくなります。
したがって、既に本人同士で離婚の合意に至りそうな場合でも、まずは一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
離婚分野における当事務所の特徴
当事務所の離婚・男女問題解決における特徴は以下の5つがあります。
1.当事務所の岡山県北地域における1年間の離婚・男女問題事件の受任は30件以上!離婚・男女問題の豊富な実績
当事務所では、これまでに岡山県北地域において,1年間に,離婚男女問題に関する受任だけで30件以上を受任して参りました。
多数のご相談や事件解決を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどをもっています。
2.調停や裁判になる前に、協議(話し合い)段階での相談に力を入れています。
離婚問題をこじらせる前に,協議の段階で解決することで,夫婦間の問題をスピード解決します。
3 依頼者との打ち合わせに力をいれています。
離婚事件は、損得だけではなく、当事者の心情に沿った解決が優先される事件です。実際の事件処理にあたって、ご本人が重要でないと思っている事実が実は重要だったというような場合もあります。このような事実や当事者のお気持ちは、弁護士と顔を合わせて打ち合わせをする中で把握されていきます。離婚事件は他の事件と比較しても弁護士との打ち合わせが重要な事件といってよいでしょう。
4.心理カウンセラーなどの専門家と連携しています。
 離婚の問題を抱えている依頼者の方には,精神的に追い詰められてる方がおられます。
離婚の問題を抱えている依頼者の方には,精神的に追い詰められてる方がおられます。
私たちは,心理面のサポートも離婚問題解決には重要であると思っています。
5.初回の相談料は無料です。電話での相談も可能です。
「弁護士に相談すると高そう」など、不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。